子どもの自己肯定感を高める10の習慣|親ができる毎日の声かけと関わり方
「どうせできない」「私なんか…」
まだ小さな子どもから、そんな言葉が聞こえてくることはありませんか?
いま、子どもの“自己肯定感”の低下が問題視されています。
実際、日本の子どもは先進国の中でも自己肯定感が特に低いと言われており、文部科学省や教育現場でも課題として取り上げられています。
- そもそも自己肯定感とは?
- こんな悩み、ありませんか?
- 自己肯定感は、家庭の中で育まれる
- 自己肯定感を高める=親の自己肯定感も大切
- 習慣①|子どもの話を最後まで「うんうん」と聞く
- 習慣②|「できたこと」に目を向けて小さくほめる
- 習慣③|「ありがとう」を意識して伝える
- 習慣④|間違えたときほど、安心できる言葉をかける
- 習慣⑤|子どもの「選ぶ力」を尊重する
- 習慣⑥|ネガティブな感情を否定しない
- 習慣⑦|「存在そのもの」を認める言葉をかける
- 習慣⑧|「ママも失敗するよ」と自然体を見せる
- 習慣⑨|子どもが好きなことに“とことん付き合う”
- 習慣⑩|「◯◯してくれてうれしい」と“感情”で伝える
- まとめ|親の関わりで、子どもの“心の土台”は育てられる
- よくあるQ&A
- チェックリスト|できるところから実践!
- さいごに
そもそも自己肯定感とは?
自己肯定感とは、「ありのままの自分を認め、尊重する気持ち」のこと。
他人と比較するのではなく、自分の存在そのものに価値を感じる力です。
この感覚は、自己信頼やチャレンジ精神、ストレス耐性、他人への優しさなど、人生を前向きに生きるための“土台”となるもの。
だからこそ、子どものうちから「自己肯定感の土壌」を育てておくことは、とても大切なのです。
こんな悩み、ありませんか?
- ちょっと注意するとすぐ落ち込む
- 「どうせ無理」が口癖になっている
- ほめても「そんなことない」と否定する
- 他人の評価ばかり気にする
こうした言動の背景には、「自分を認められていない」「どうせ失敗すると思っている」など、自己否定のクセがある場合が多いのです。
自己肯定感は、家庭の中で育まれる
自己肯定感は、特別な教育を受けなければ育たないものではありません。
むしろ、家庭での「ちょっとした関わり方」や「声かけ」こそが、一番の栄養になります。
・子どもの話にどう耳を傾けるか
・失敗したときにどんな言葉をかけるか
・日常の中でどんな表情で接するか
このような「毎日の積み重ね」が、子どもの心の中に「私は大切にされている」「できるかもしれない」という土台を作っていくのです。
自己肯定感を高める=親の自己肯定感も大切
「もっと子どもを認めなきゃ」と思っても、自分自身に余裕がないと、ついイライラしてしまうこともありますよね。
実は、子どもの自己肯定感を育てるには、親自身が自分を肯定できていることもとても大切です。
「今日も頑張ったな」「できなくてもいいか」
そんなふうに、自分を許す・認める姿を見せることも、子どもにとっての自己肯定感のモデルになります。

習慣①|子どもの話を最後まで「うんうん」と聞く
「ママ、今日ね…」「うん、あとでね」
忙しい毎日、ついこうした返しをしてしまうことはありませんか?
でも実は、子どもが「話をちゃんと聞いてもらえた」と感じることは、自己肯定感の基盤になります。
なぜ効果的?
心理学では「アクティブリスニング(積極的傾聴)」と呼ばれるこの関わり方が、共感・自己受容感・親子信頼感を高める効果があるとされています。
ポイントは3つ
- 子どもが話しかけてきたら、目線を合わせる
- うなずきや「へえ〜」「そうなんだ!」などの反応を入れる
- 途中で口を挟まず、最後まで聞く
体験談:
「子どもの“しょうもない話”にもちゃんと反応していたら、自然と『今日こんなことあったよ』と話してくれるようになりました」(30代・主婦)
おすすめアイテム
忙しい時でも話を遮らない工夫に、子ども専用“おしゃべりタイムノート”を作るのもおすすめ。書いてもらってあとでじっくり読むのも立派な傾聴です。

習慣②|「できたこと」に目を向けて小さくほめる
子どもがなにかを頑張ったとき、つい「もっとこうすればよかったのに」と指摘していませんか?
自己肯定感を育てるには、まず「できたこと」に目を向けて言葉にすることがとても大切です。
自己効力感と肯定感の関係
「ほめられた=認めてもらえた」と感じることで、自分にもできる!という自己効力感が高まり、それが自己肯定感の基盤になります。
具体的な声かけ例
- ×「ちゃんと最後までできた?」 → ○「自分から始めたのがすごいね」
- ×「もっと早くできたでしょ」 → ○「途中でやめずに続けたの、偉かったね」
体験談:
「“小さなできた”を見つけて伝えるようになってから、子どもが『これやったよ!』と自信を持って見せてくれるようになりました」(40代・共働き家庭)
おすすめアイテム
「できたこと」を記録していけるシールカレンダーや、おうちほめ日記など、形に残るアイテムも◎
習慣③|「ありがとう」を意識して伝える
子どもに対して、「ありがとう」と伝えていますか?
つい「〇〇してって言ったでしょ!」「早くして!」と指示や注意が多くなってしまいがちですが、子どもが“自分が役に立っている”と感じる経験こそ、自己肯定感を高める栄養です。
なぜ「ありがとう」が効く?
心理学では「自己有用感」という言葉があります。
これは、「自分は誰かの役に立てる存在なんだ」と感じる力で、自己肯定感と強く関係しています。
言葉の例
- 「お手伝いしてくれて、助かったよ!ありがとう」
- 「今日も元気にいてくれて、ママはうれしいな」
何かしてくれたときだけでなく、存在そのものにありがとうを伝えることも効果的です。
体験談:
「“ありがとう”を意識して伝えるようになってから、子どもが『ママ、ありがとう』と返してくれるようになって、親の私の心も癒されています」(30代・会社員)
おすすめアイテム
「ありがとう」を言いやすくする習慣化ツールに、親子で交換日記などもおすすめです。

習慣④|間違えたときほど、安心できる言葉をかける
子どもが失敗したとき、「なんでそんなことしたの!」と怒っていませんか?
失敗の場面こそ、親の対応が子どもの“自分への見方”を左右するタイミングです。
失敗=成長の種に変える声かけ
「失敗しても受け入れてもらえる」という安心感が、挑戦する勇気=自己肯定感を支えます。
おすすめの言葉
- 「失敗しても大丈夫。やってみたのがすごいよ」
- 「ママも子どものころ、いっぱい失敗したよ」
間違えた自分を否定せず、「やってみたこと」を認めてもらえる体験が大切です。
体験談:
「怒る代わりに『一緒にやり直してみようか』と伝えたら、子どもが『もう一回やってみる!』と前向きになりました」(40代・パート主婦)
おすすめアイテム
「失敗は宝物」と伝える絵本や、感情を整理する親子対話カードも有効です。
習慣⑤|子どもの「選ぶ力」を尊重する
日々の生活の中で、子どもが自分で選べる場面を意識的に増やしていますか?
「この服にしなさい」「こっちの方がいいよ」
そんな親の“正解”が先に出てしまうと、子どもは自分の選択に自信が持てなくなってしまいます。
選択=自己決定のトレーニング
選ぶという経験は、「自分で決めて行動した」という成功体験につながります。
これは自己決定感を育み、自己肯定感の土台を支えるものです。
実践例
- 「今日は青の服と赤の服、どっちが着たい?」
- 「この本とこの本、どっち読みたい?」
- 「今日のごはん、どっちがいいかな?」
選択肢を2〜3つ用意し、その中で選んでもらうのがポイントです。
体験談:
「小さな“選ばせ”を増やしてから、子どもが『自分で決める!』と言うようになって驚きました」(30代・2児の母)
おすすめアイテム
毎日の選択を視覚化できる選べる朝ルーティンカードや、着替えボードなども便利です。

習慣⑥|ネガティブな感情を否定しない
子どもが泣いたり怒ったりしたとき、「泣かないの!」「怒っちゃダメでしょ!」と言ってしまっていませんか?
実はその言葉、子どもの“感情そのもの”を否定してしまっている可能性があります。
感情=その子の一部
感情をそのまま受け止めてもらえる体験は、「どんな自分でもOK」と感じられる根っこになります。
これは、自己肯定感の最も重要な要素です。
こんなふうに変えてみよう
- ×「泣かないの!」 → ○「泣きたいくらい悲しかったんだね」
- ×「怒るのやめて」 → ○「すごくイヤだったんだね」
感情に名前をつけるだけでも、子どもは「わかってくれた」と感じられます。
体験談:
「怒っているときに『悲しかった?』と聞くようにしたら、『うん』と気持ちを伝えてくれるようになりました」(40代・小学生の母)
おすすめアイテム
感情に名前をつけられる気持ちカードや絵本も、子どもが自分の感情を理解するサポートになります。
習慣⑦|「存在そのもの」を認める言葉をかける
多くの親がやりがちなのが、「できたこと」や「頑張ったこと」ばかりを褒めてしまうこと。
でも実は、“何もしていないときの子ども”こそ肯定されるべき存在です。
条件付きの承認では育たない
「◯◯ができたから偉いね」という褒め方だけだと、子どもは「できない自分は価値がないのかも」と感じてしまいます。
こんな声かけを意識しよう
- 「あなたがいてくれるだけで、うれしいな」
- 「大好きだよ」「生まれてきてくれてありがとう」
これは、自己肯定感の根っこ=無条件の愛を伝えるための言葉。
特別な日に限らず、日常的に伝えていきましょう。
体験談:
「寝かしつけのときに“今日もいてくれてありがとう”と言っていたら、子どもからも“ママもありがとう”と言ってくれるように」(30代・会社員)
おすすめアイテム
「存在を認める」メッセージが込められた絵本や、親子で読み聞かせできるありがとう日記がおすすめです。
習慣⑧|「ママも失敗するよ」と自然体を見せる
親が完璧でいようとすればするほど、子どもは「自分も完璧じゃなきゃ」と思ってしまいます。
逆に、親が“失敗しても平気な姿”を見せることが、子どもの自己肯定感にとって重要な学びになります。
失敗を“見せる”勇気
「あ〜間違えちゃった!でも大丈夫!」
そんな言葉を笑って言える親の姿は、「失敗してもOK」という安心感につながります。
親の自然体を伝えるコツ
- 「ママも小さいころ〇〇できなかったよ」
- 「今日ちょっと失敗しちゃった〜、でもまたやってみるよ」
これだけで、子どもは「完璧じゃなくてもいいんだ」と思えるようになります。
体験談:
「うっかり失敗したときに“まぁいっか”と声に出していたら、子どもも“失敗しても大丈夫なんだ”と口にするように」(40代・共働き家庭)
おすすめアイテム
「失敗は宝だよ」と伝える子ども向け絵本や、親子で読むエッセイ本なども役立ちます。
習慣⑨|子どもが好きなことに“とことん付き合う”
「また恐竜の話?」「ずっと同じ絵本読んでるね」
そんなふうに思っても、子どもが夢中になっていることに共感する姿勢は、自己肯定感に直結します。
“好き”を尊重する=存在の尊重
子どもの「好き」「楽しい」は、その子らしさの表れ。
それを受け止めてもらえることで、「私はこのままでいいんだ」という自己肯定の土台が育まれます。
付き合い方の工夫
- 興味のある図鑑を一緒に読む
- 好きな絵を一緒に描いて飾る
- 「これはなんで好きなの?」と聞いてみる
「いいね」「教えてくれてありがとう」などの声かけが子どもの誇りを育てます。
体験談:
「何百回も同じ電車図鑑に付き合っていたら、息子が『ぼく、電車博士なんだよ!』と自信満々に言ってきてくれました」(30代・主婦)
おすすめアイテム
図鑑、ぬりえ、工作セットなど“好き”を広げられる知育系アイテムが◎
習慣⑩|「◯◯してくれてうれしい」と“感情”で伝える
「上手だね」「すごいね」だけでなく、親の“気持ち”を伝えることも、子どもの自己肯定感を育てる大きなポイントです。
なぜ“感情”が効くのか?
「ママがうれしい」「パパが安心したよ」など、行動が誰かの心を動かしたことを実感できると、子どもは自分の存在価値を深く感じられるようになります。
言葉のバリエーション
- 「手伝ってくれてうれしかったよ」
- 「お片づけしてくれて助かっちゃった」
- 「笑ってくれるとママ、元気になるなあ」
“褒める”ではなく、“感謝”+“感情”をセットにして伝えるのがコツです。
体験談:
「“ありがとう”だけじゃなく“うれしい”と伝えるようにしたら、娘がニコッと笑って“じゃあもっとやる!”と積極的になってくれました」(40代・ワーママ)
おすすめアイテム
感情表現カードや親子向けの感情日記なども、感情を伝え合う練習になります。
まとめ|親の関わりで、子どもの“心の土台”は育てられる
子どもの自己肯定感は、特別な教育や高額な習い事で育つものではありません。
日常のなにげない声かけ、表情、反応――それらの積み重ねが、子どもの「自分は大切にされている」「そのままで価値がある」と感じる心を育てていきます。
親だって完璧である必要はありません。
今日から一つずつ、やってみようかな。
そんな気持ちが、きっと子どもに届いていきます。
よくあるQ&A
Q1. 自己肯定感を育てるには、何歳ごろから意識すればいいの?
A. 幼児期から意識するのがベストですが、小学生以上でも遅くはありません。
年齢に応じた関わり方で、何歳からでも心の土台は育てられます。
Q2. 兄弟がいると、どうしても比べてしまいます…
A. 比較そのものが悪いのではなく、「比べた結果どう声をかけるか」が大事です。
「上の子の方がすごいね」ではなく「あなたのここが素敵だよ」と個性に注目した声かけを意識してみましょう。
Q3. 子どもが「どうせ無理」と言ったとき、どう返せばいい?
A. 否定せず、共感してから励ましましょう。
「そう思っちゃう時もあるよね。でも、やってみようと思っただけでもすごいよ」といった言葉がけが効果的です。
チェックリスト|できるところから実践!
| 習慣 | できた? |
|---|---|
| ① 子どもの話を最後まで聞く | ☐ |
| ② 小さな成功を見つけてほめる | ☐ |
| ③ 「ありがとう」を伝える | ☐ |
| ④ 失敗したときこそ安心感を | ☐ |
| ⑤ 子どもに選ばせる習慣をつくる | ☐ |
| ⑥ ネガティブ感情を否定しない | ☐ |
| ⑦ 存在そのものを肯定する | ☐ |
| ⑧ 親の自然体・失敗も見せる | ☐ |
| ⑨ 好きなことにとことん付き合う | ☐ |
| ⑩ 感情をセットにして伝える | ☐ |
さいごに
自己肯定感は、目に見えないけれど一生を左右する“心の栄養”。
今日の一歩が、きっと未来の笑顔につながります。
焦らず、完璧を目指さず、親子で育ちあう時間を大切にしていきましょう。
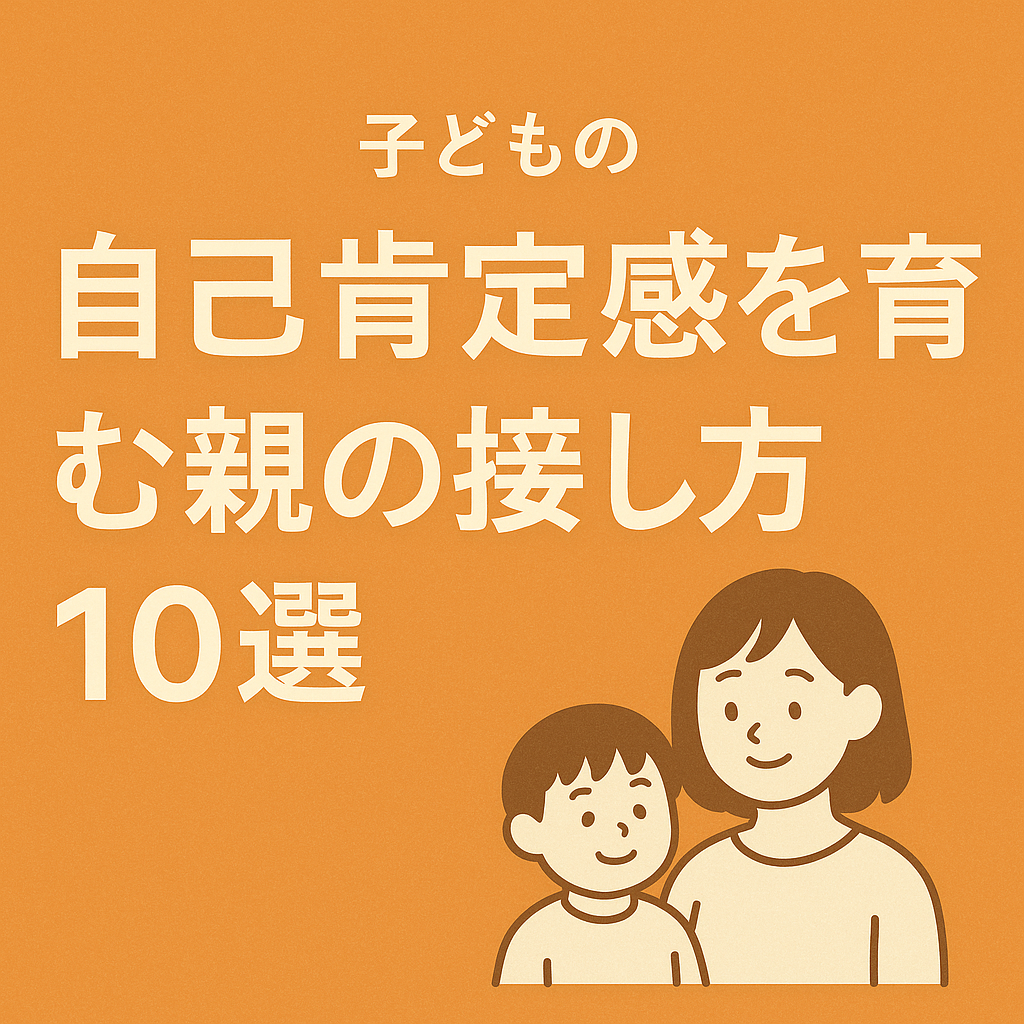


コメント